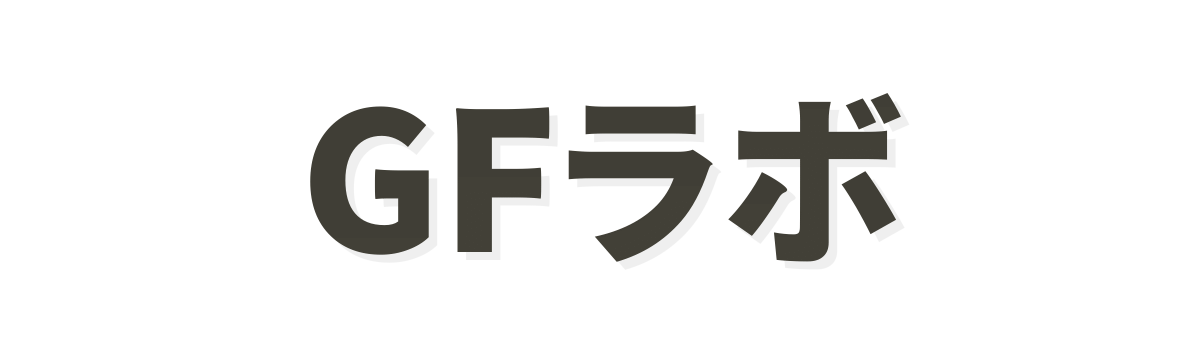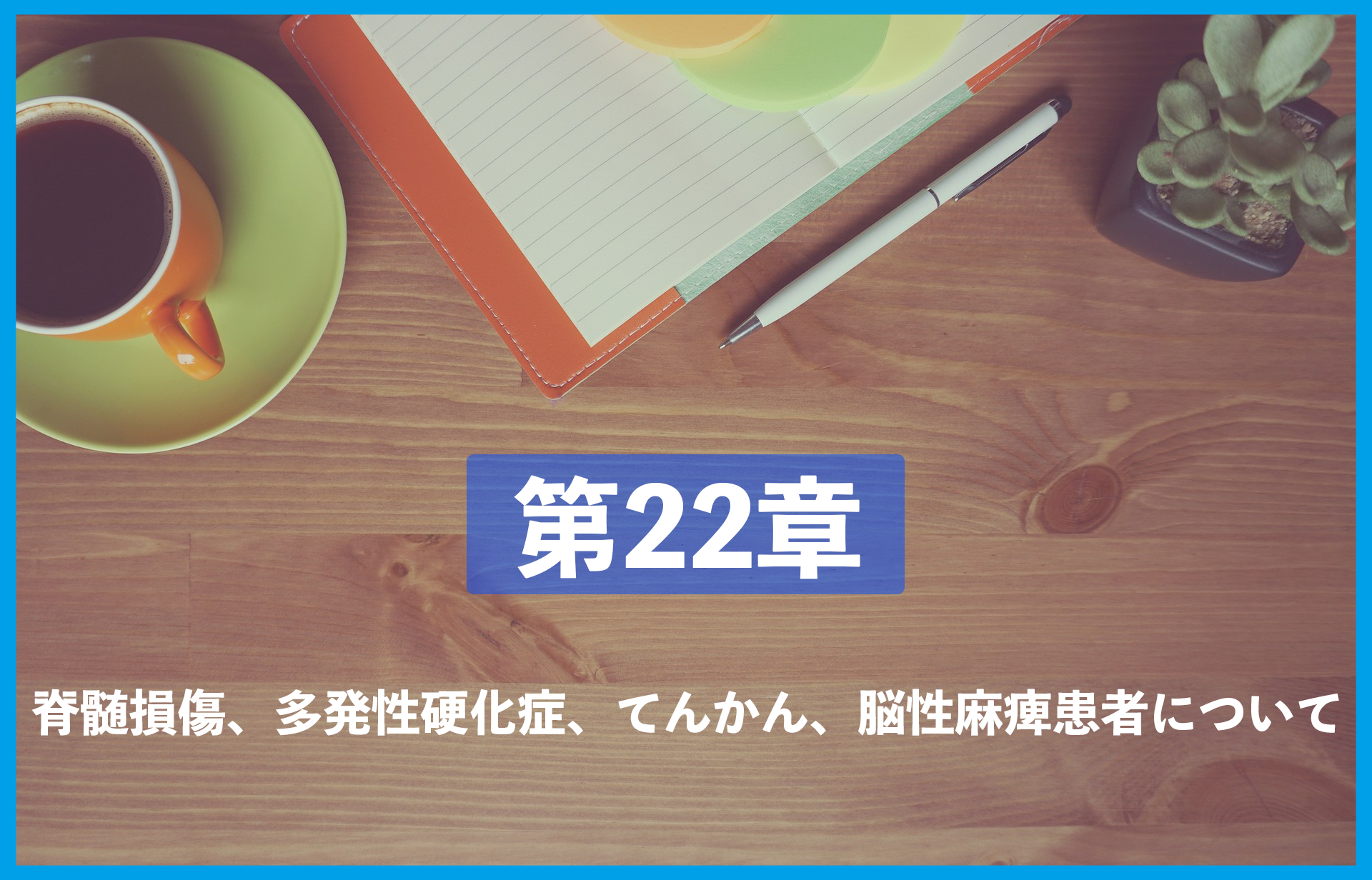NSCA-CPT 試験対策
分野別問題集
- 【第1章】筋系,神経系,骨格系,の構造と機能
- 【第2章】心肺系の構造と機能
- 【第3章】生体エネルギー機構
- 【第4章】バイオメカニクス
- 【第5章】レジスタンストレーニングに対する反応と適応
- 【第6章】有酸素性持久系トレーニングへの反応と適応
- 【第7章】栄養摂取に関する考え方と方法
- 【第8章】運動心理学、目標設定、動機付け
- 【第9章】クライアントの面談と健康評価
- 【第10章】体力の評価、選択、管理
- 【第11章】体力評価法と評価基準
- 【第12章】柔軟性とウォームアップの概念および自重、スタビリティボールエクササイズテクニック
- 【第13章】レジスタンスエクササイズテクニック
- 【第14章】心臓血管系エクササイズのテクニック
- 【第15章】レジスタンストレーニングのプログラムデザイン
- 【第16章】有酸素性トレーニングのプログラムデザイン
- 【第17章】プライオメトリックトレーニングとスピードトレーニングのプログラムデザインとテクニック
- 【第18章】前青年期の子ども、高齢者、妊婦のクライアント
- 【第19章】栄養や代謝に問題を抱えるクライアント
- 【第20章】心血管疾患および呼吸器系疾患を有するクライアント
- 【第21章】整形外科的疾患や傷害を有するクライアントとリハビリテーション
- 【第22章】脊髄損傷、多発性硬化症、てんかん、脳性麻痺を有するクライアント
- 【第23章】アスリートを対象にしたレジスタンストレーニング
- 【第24章】施設と機器の配置およびメンテナンス
- 【第25章】パーソナルトレーナーの専門的、法的および倫理的責任
試験対策問題集
暗記項目すべて
動画問題対策
その他の対策集
NSCA-CPT関連記事